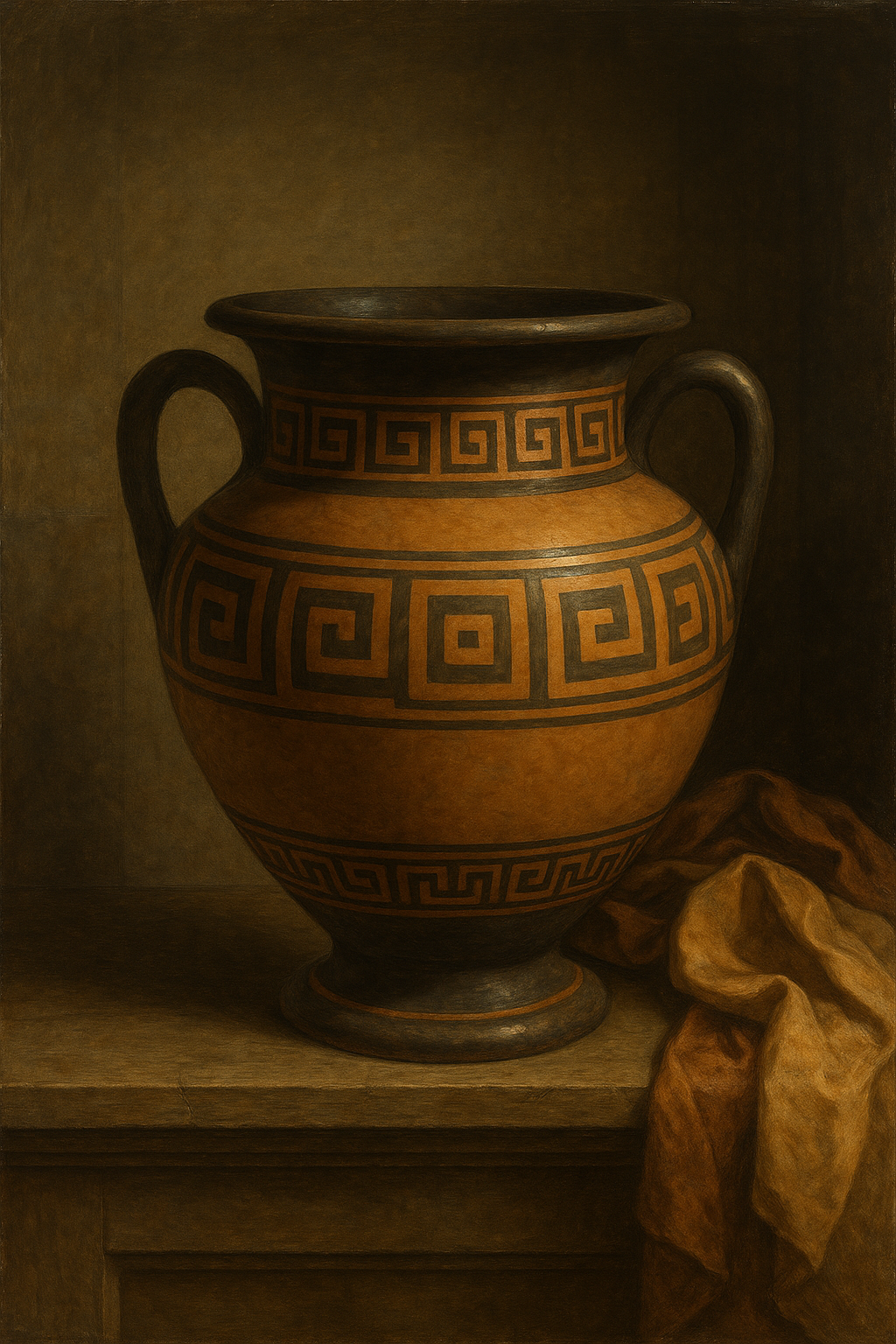ゴシック装飾におけるユニコーン ─ 純潔と神秘を象徴する伝説の獣
ユニコーンの起源

ユニコーン(Unicorn)は、一本の長い角を持つ幻獣として、西洋・中東・アジアの複数の文化に登場します。
古代ギリシャの博物学者クテシアスがインドの動物として記述したのが、西洋史料での初出とされます。
その後ローマ時代や中世ヨーロッパの文献に広まり、キリスト教文化と結びつくことで象徴性が強まりました。
中世・ゴシック装飾でのユニコーン
ゴシック期(12〜15世紀頃)の聖堂建築や写本装飾、タペストリーにはユニコーンが頻繁に登場します。
特にステンドグラスや彫刻では、以下のような意味が込められました。
-
純潔・貞節:ユニコーンは処女にのみ心を許すとされ、聖母マリアの象徴と結びつきました。
-
神秘と信仰:捕らえることが難しい存在として、「神の恩寵」や「救済の神秘」を象徴。
-
守護・高貴さ:教会や王家の紋章に描かれ、権威と高潔さを表現。
ユニコーンの図案は中世ヨーロッパにおいてタペストリーの題材として非常に好まれ有名なものには「貴婦人と一角獣」「囚われのユニコーン」が有名です。
甲冑の兜部分の装飾に用いられたものを見たことがありますが、透かし彫りになっているので実用を考えた装飾ではなくあくまで財力を示すためのもののようでした。
ユニコーンの宗教的意味と教会装飾での位置づけ
-
聖母マリアの象徴
中世の動物寓話集「フィジオロゴス」では、ユニコーンは処女にしか捕らえられないとされ、この「処女」をマリア、ユニコーンをキリストになぞらえる解釈が広まりました。 -
受肉(受胎告知)の象徴
ユニコーンが乙女の膝に頭を乗せる場面は、キリストが人の子として宿る瞬間の寓話的表現とされ、ステンドグラスや写本の挿絵に使われました。
実在する代表例
ステンドグラス
-
シャルトル大聖堂(フランス)
-
西側ファサードや聖母礼拝堂のステンドグラスに、ユニコーンと乙女のモチーフが見られます。
-
-
シャンティイ城の「貴婦人と一角獣」連作(現・クリュニー中世美術館)
-
こちらはステンドグラスではなくタペストリーですが、ユニコーンが描かれたものと言えばという代表的なもので修道院文化圏で制作され、同時代のステンドグラス意匠にも影響を与えたとされます。
-
-
スイス・バーゼル大聖堂
-
14世紀頃のステンドグラスに、ユニコーンと聖母マリアを組み合わせた図像が残っています。
-
建築彫刻
-
フランス・アミアン大聖堂
-
ドイツ・レーゲンスブルク大聖堂
-
英国の修道院跡(例:フォントヒル修道院)
用いられ方の特徴
-
位置:聖母礼拝堂・側廊の小礼拝室・聖具室の装飾に多い。
-
場面:乙女とユニコーン、または楽園の動物群の一部として登場。
-
意匠:ステンドグラスでは明快なシルエットと角を強調、建築彫刻では絡み合う蔓草や聖書場面と組み合わせ。
象徴性の変化
-
中世前期:聖書の寓話や宗教的象徴としての側面が強い。
-
ルネサンス以降:恋愛や貴族文化における理想像としてのユニコーンが増え、宝飾品や世俗的装飾にも広がる。
-
近代〜現代:ファンタジーやポップカルチャーでの人気が再燃し、柔らかく可愛らしいイメージへ変化。
最初期にあった角に猛毒を持っている、その角で象をも倒すという設定は今ではほとんどなくなっていますね。
ゴシック装飾に見るユニコーンの造形特徴
-
細長くねじれた一本角
-
馬に似た体躯に、時にヤギや鹿のような足
-
流れるたてがみと尾、尾はライオンの尾とされることもあります。
-
荘厳で落ち着いたポーズ(跳躍ではなく静立)
これらは彫刻や彩色写本の中で、細密な装飾と組み合わされ、空間に神秘性を与えます。
現代のデザイン活用
現代においてユニコーンは「唯一無二」「希少性」「高潔さ」を表すモチーフとして解釈されています。
また描かれ方も多岐にわたるようになっており、誕生期にはヤギの特徴が多く見られた顎髭や割れた蹄という造形も現代のユニコーンではほとんど見られなくなり、白馬に角が生えた姿になっていることが少なくありません。